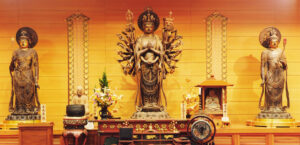古墳は、日本全国に約16万基ほどあるという。
その数の多さを表現するために、よく「コンビニより多い」と表現される。
日本全国にあまねく古墳がある以上、我々の祖先は、すべて古墳づくりに携わったはずである。
もちろん、つくった側でなく、つくられた側の子孫もいるであろう。
古墳の姿として我々が思い浮かべるのは、緑の木々に覆われた姿である。
ただ、最初からその姿ではなかった。
最初は土だけ、もっと正確に言うと「葺石(ふきいし)」と呼ばれる河原石で覆われた姿であった。
群馬県の八幡塚古墳のように、つくられた当時の姿を復元している古墳もある。

八幡塚古墳(群馬県)
形については、前方後円墳が有名であるが、ほかに円墳や方墳といったものがよく知られている。
大きさについては、小さいものは数メートルから、大きいものは大王墓の数百メートルまで、幅広い。
(古墳時代後期には、有力農民も小さな古墳を作るようになった)
古墳を訪ねたとき、最初に感じることは「これを大昔の人が人力で作り上げたんだ」という、いにしえへのロマン。
そして、かつては葺石で覆われた華やかな姿を見せていたであろう古墳が、今は草ふかい田舎に埋もれるように存在する姿を見たときの、無常観。
とにもかくにも、また古墳を訪ねてみようかな。